くり下がりのあるひき算には、大きく2つのやり方があります。
ひとつは「減加法」、もうひとつは「減減法」と呼ばれるやり方です。
それぞれに長所があり、状況に応じて使い分けができるとよいのですが、学校の授業で両方の指導に十分な時間を割くことはまれです。
そのため、家庭での指導が必要になってきます。
そこで、今回の記事では、「くり下がりのあるひき算の学習に、家庭でどう取り組めばよいか」についてお話ししたいと思います。
13-9 はどうやって計算する? 11-2 は? 16-8は?
まずは、13-9、11-2、16-8について、減加法と減減法でのやり方を見てみましょう。
どちらが計算しやすいか、比べてみてください。
= 1+3 👈 10から9を引いて1
= 4 👈 1と3で4
= 10-6 👈 13から3を引いて10
= 4 👈 10から6を引いて4
= 8+1 👈 10から2を引いて8
= 9 👈 8と1で4
= 10-1 👈 11から1を引いて10
= 9 👈 10から1を引いて9
= 2+6 👈 10から8を引いて2
= 8 👈 2と6で8
= 10-2 👈 16から6を引いて10
= 8 👈 10から2を引いて8
どちらがやりやすかったでしょうか?
それぞれにメリットとデメリットがあり、馴れ不慣れの問題もあるので一概にはいえないのですが、(1)は減加法でやる人が多いと思います。
(2)は減減法でやる人が多いでしょう。
(3)はどちらもやりやすいと思いますが、減加法がやや優勢かもしれません。
減加法と減減法 それぞれのメリットとデメリット
では、それぞれの方法のメリットとデメリットを見ていきましょう。
・ひく数が大きいとき(7や8や9のとき)
(例)13-9、120-80
・ひく数が5のき
(例)11-5、130-50
・ひく数が小さいとき(2や3や4のとき)
(例)11-2、120-40
・ひく数とひかれる数の同じ桁の数の差が小さいとき
(例)16-7、170-80
※ 導入期は、減減法の学習を通じて、数の合成・分解の習熟が進むという考え方もあります。
(計算の例)
= 60+13-5
= 73-5
= 70-5+3
= 65+3
= 68
(計算の例)
=103-35
=103-30-5
= 73-5
= 73-3-2
= 70-2
= 68
このように、どちらにも長所と短所、数の組み合わせ対する向き不向きがあります。
学校の授業ではどう教えている?
小学校での指導は、減加法が中心になることが多いです。
『小学校学習指導要領解説 算数編』(平成29年7月 文部科学省)は、
「どちらを主にして指導するかは、数の大きさに従い柔軟に対応できるようにすることを原則とするが、児童の実態に合わせて指導することが大切である。」
としています。
しかし、公立の小学校で採択されている教科書の大半は、減加法を中心に扱っています。
また、教育現場としても、限られた時間の中で生徒全員に一定レベルの計算力を保障しなければならないことから、減減法の指導に十分な時間を割くことができないようです。
では、なぜ減減法ではなく 、減加法なのでしょうか?
一つには、減加法の「ひかれる数を10といくつに分解して、10から引く」という単純で一貫した手順が、学童初期の子どもには理解しやすく、定着しやすいと考えられているからです。
また、「減加法の考え方が筆算の繰り下がりの操作と一致する」というのも理由の一つでしょう。
「減加法をきちんと学習しておくと、筆算の学習がスムーズに進む」と考えられているようです。
結局、どう指導するのがよい?
とはいえ、減減法の習得が必要ないのかというと、そんなことはありません。
まず、3ケタ、4ケタの暗算では、減減法が便利な場面も多いです。
また、ナンバーセンスを育てるという意味でも、減減法の学習は必要です。
「減加法」一辺倒では、「柔軟に対応する」機会が生まれるはずもありません。
そのようなことから、減加法と減減法のどちらも、しっかり練習しておくことをおすすめします
指導のしかた
指導のしかたとしては、僕の場合、最初のうちは個々の計算について、どちらがやりやすいか比較させるようにしています。
たとえばドリルなどをやるとき、ノートを縦に二等分して、一問一問、両方のやり方で計算させ、どちらがやりやすいかを評価させます。
減加法の学習が先行している子どもには、ドリルの1巡目は減加法、2巡目は減減法、というやりかたでもよいです。
この方法でドリルなどをひととおり終えるころには、数の大きさによって柔軟に対応するようになっているはずです。
減加法を用いるか減減法を用いるか、正解はある?
数のどの組み合わせを減加法で、または減減法でやるかは、その人しだいです。
どちらがやりやすいか、全体的な傾向はありますが、正解はありません。
一般に、
13-9、16-8のように、引く数が10に近いときは、減加法がやりやすい
11-2、16-8のように、引かれる数の一の位の数と引く数の差が小さいときは、減減法がやりやすい
ということは言えます。
どちらか一方だけを使うのではなく、使い分けができていれば、それでよいと思います。
ちなみに、僕の場合はこうなります。
(1) 13-9 減加法
(2) 11-2 減減法
(3) 16-8 減減法(16-9なら減加法)
だいたい一般的な傾向と同じですね。
まとめ
くり下がりのあるひき算では、減加法と減減法の両方を習得する必要があります。
最終的には、数の組み合わせに応じて、自分が計算しやすいほうを自然に選択して計算できるようになればよいです。
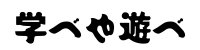
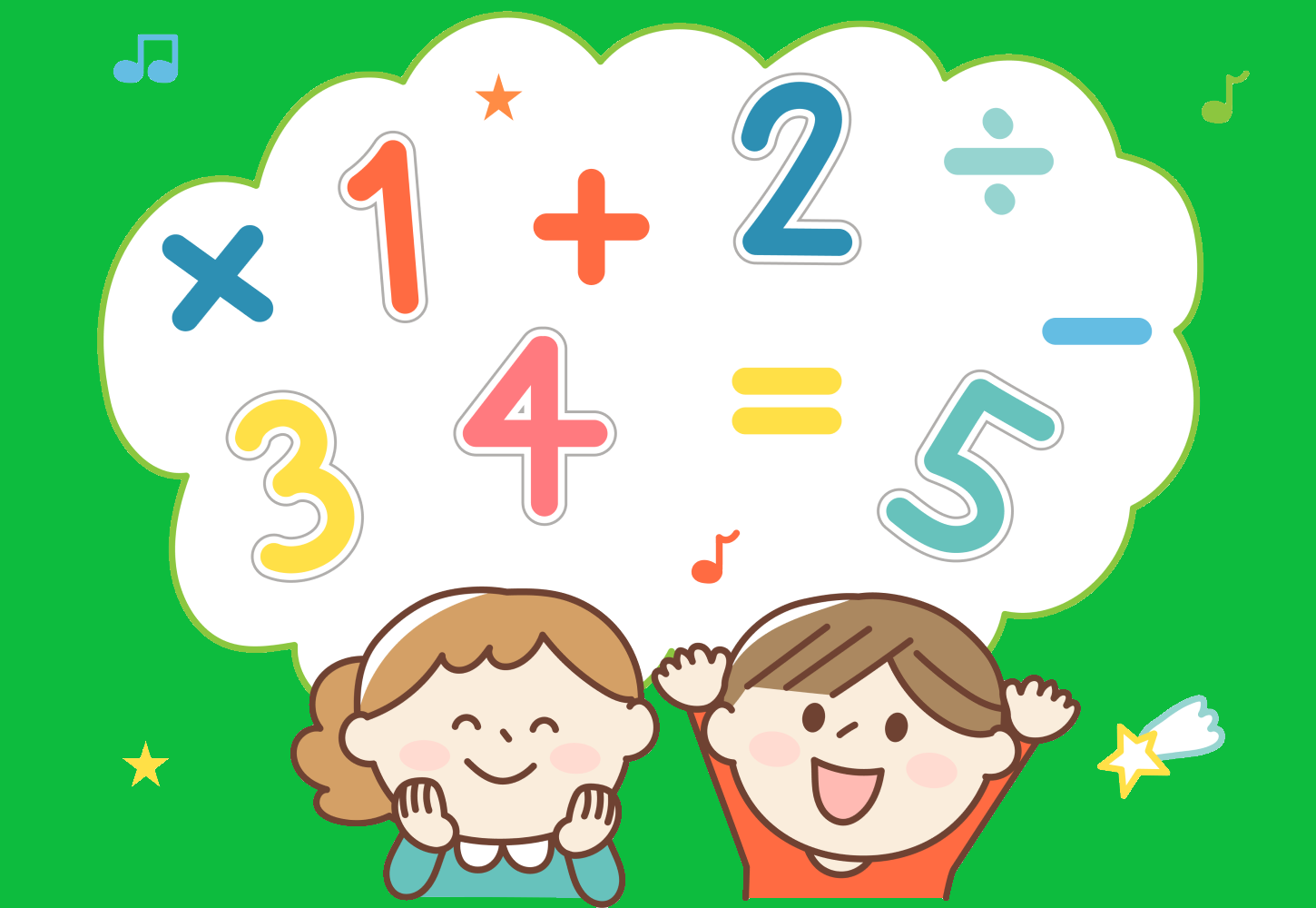
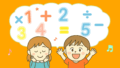
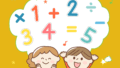
子どもの学びに関する多くの学術的知見を持っています。
また、6歳児から中高校生まで勉強を教えた経験があり、学力に与える学習の効果は、年齢が低いほど大きいことを痛感しています。
これらを生かして、効果的で再現性の高い子どもの学びのあり方や方法を提案していきます。よろしくお願いします。