数の力を身につける18ステップ!
家庭でできるチェック&トレーニング【ステップ2】
習得目標年齢:3歳
数が唱えられるようになると、その範囲でものを数えることが可能になります。
その第一歩は、数える対象の一つ一つに数詞を「いち、に、さん、・・・」と割り振ることです。
【課題】ものを指でさしながら声に出して数える
おはじきを10個並べて、その一つ一つを指でさしながら「いち、に、さん、…」と声に出して数える。
※ 「おはじき」を使用していますが、機能が類似するものなら何でもよいです(全てのステップ共通)。
チェックポイント
この課題のチェックポイントは、おはじきを指でさしながら数えるとき、1つのおはじきに一つの数詞(いち、に、さん、・・)が必ず1回だけ割り振られることです。
つまり、飛ばしや重複がないことです。
これができると、計数を可能にする5つの原理(下記参照)のうちの「一対一対応」と「安定した順序」の二つが理解できていることになります。
なお、この段階では、「最後に唱えた数が、全体の個数を表していること(基数性)」を理解していなくても問題はありません。
「基数の原理」の理解は、日常生活の中で個数を扱うことにより、徐々に理解していきます。
練習のポイント
子どもが、まだ「一対一対応」できちんと数えられない場合は、教示者が手本を見せて、それに倣わせるようにします。
そうやって、まずは5個を確実に数えられるようにします。
一対一対応で10個まで数えることができたら、次のステップに進むことができますが、その後も数えられる個数を15、20と延ばしていきます。
さしあたっては、20個ぐらいまで数えられるようにしておけばよいでしょう。
計数を可能にする5つの原理
幼児がものを数えていくつあるかを認識するには、次の5つの原理を理解する必要があるといわれています。(Gelman & Gallistel, 1986)
- 一対一対応:もの数えるとき、数えるものの一つ一つに、必ず数詞(いち、に、さん、・・)が一つ、割り振られる
- 安定した順序:ものを数えるとき、「いち、に、さん、・・」、「ひ、ふ、み、・・」というように、数詞の順序は常に一定である
- 順序無関連:ものを数えるとき、どれから、どの順番で数えても全体の数は変わらない
- 基数性:ものを数えるとき、最後に唱えた数は、全体の数を表している
- 抽象性:数える対象が何であっても(車でも動物でも野菜でも)、1~4の原理が適用される
10まで数えられるようになったら
10まで数えられるようになったら、少しづつ数字も覚えていきましょう。
数字を早めに覚えることは、子どもが数の知識とスキルを習得するうえで、とても有利に働きます。
子どもが数字を覚えるには、数字に触れる機会を親が設けてあげる必要があります。
たとえば、お風呂に数字の表を貼って一緒に読む(推奨)、数字がでてくる絵本を一緒に読む、数字をテーマにしたおもちゃで遊ぶ、といった機会をつくります。
また、普段の生活の中で、身の回りの数字にできるだけ触れさせるようにします。
たとえば、「(時計の)長い針が5のところにきたら、出発するよ」とあえて言ったり、「(リモコンの)8を押してくれる?」とあえて頼んだりします。
このようにして、まずは10までの数字を覚えるようにしましょう。
【数字ポスターの選び方のポイント】
・100までの数字が表になっているもの(100以上ならよい)
・一の位の数が列ごとに揃っているもの(11~100が揃っていればよい)
以下は、家庭の学びのスタイル、お子さんの発達状況に合わせて選択
・数字に読み仮名がついているかどうか
・お風呂に貼れるかどうか
・1~10に具体物の例があるかどうか
- Gelman, R., & Gallistel, C. R. (1986). The child’s understanding of number. Harvard University Press.
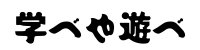
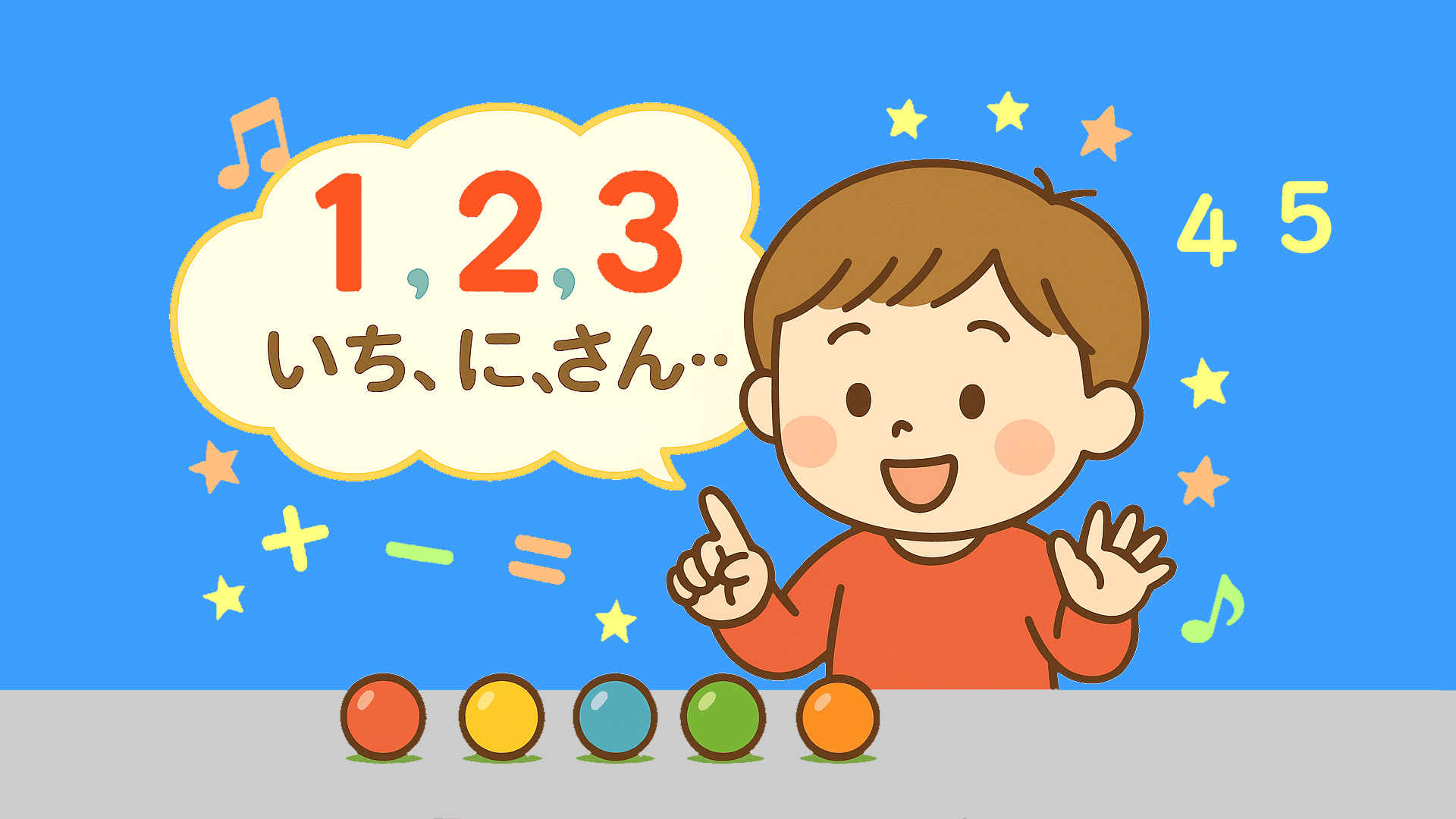



子どもの学びに関する多くの学術的知見を持っています。
また、6歳児から中高校生まで勉強を教えた経験があり、学力に与える学習の効果は、年齢が低いほど大きいことを痛感しています。
これらを生かして、効果的で再現性の高い子どもの学びのあり方や方法を提案していきます。よろしくお願いします。