数の力を身につける18ステップ!
家庭でできるチェック&トレーニング【ステップ3】
習得目標年齢:3歳半~4歳半
「一対一対応」の次のステップは、最後に唱えた数を「個数」として認識することです(基数の原理)。
これが達成されると、さまざまな数的なやり取りや活動が可能になり、数の概念形成が加速的に進んでいきます。
そのため、これを早期に達成した子どもほど、就学時の数体系の知識レベルが高くなり(Geary et al., 2018)、その後の算数の学習が順調に進んでいく可能性が高くなります。
それでは、【ステップ3】の課題を見ていきましょう。
課題は3つです。
【課題1】並べたおはじきの個数を把握する(5個まで)
用意するもの:
おはじき(5個)
手続き
- おはじき3個を一列に並べて、「何個?」と尋ねる。
- 子どもが「いち、に、さん」と数えて「3個」と答えた場合は、「じゃあ、反対から数えたら何個?」と尋ねる。
チェックポイント
この課題のチェックポイントは、3個の並んだおはじきを、端から「いち,に,さん」と数えて、またはサビタイジング(視覚的な把握)によって、「3個」と答えられることです。
また、数えて把握した場合は、「反対から数えたら何個?」と尋ねて、「(反対から数えても)3個」と数えずに即答できることです。(サビタイジングによって把握した場合は必要ありません。)
この課題がクリアできた子どもは、ステップ2で解説した「順序無関連」と「基数の原理」を理解していると判断してよいでしょう。
このようにして、「具体物の集合を数詞に置きかえる」ことができたら、次は「数詞を具体物の集合に置きかえる」ことができるかどうかも確認しておきます(課題2へ)。
【課題2】指定された個数を取り出す(10個まで)
用意するもの:
おはじき(10個以上)
手続き
おはじきの山(10個以上)を子どもの前に置き、「3個ちょうだい」、「3個取って」などと言って、指定した個数を取り出してもらいます。
このような手続きを、まずは5個までの個数で行います。
チェックポイント
この課題のチェックポイントは、「1個、2個、・・」と言いながら一つずつ取り出していって、指定された個数で停止できることです。
5個までの個数が確実に取り出せるようなら、「基数の原理」を理解していることは間違いないので、あとはその数を増やしていきます(このあと解説)。
幼児は5までの数の処理を通して整数構造を理解する
幼児は5までの数の処理を通して整数構造を理解し、しだいにその範囲を拡大していきます。
したがって、まずは5まで数を確実に扱えるようにすることが目標となります。(たとえば、栗山, 1993; 丸山, 無藤, 1997)
その際、3個と4個または5個とでは、難易度に差があることがわかっています。
これは、4個や5個になると視覚的に個数を把握するサビタイジングが難しくなり、計数(数えること)が必要になるからだと考えられています。(Chi & Klahr, 1975)
そのため、初期の数の操作では、3個から4個、5個と一つずつ増やしていくようにするとよいでしょう。
「基数(集合数)」が理解できていない子どもには
基数の原理がまだ十分に理解できていない子どもには、日常の生活の中で、「いくつある」という概念の理解を促していきます。
たとえば、キャンディーなどを与えるときに、「3個あげるね」と前置きしてから、「1個、2個、3個」と数えながら与えるとか、「1個ちょうだい」、「2つ取って」といった働きかけを意識して行うようにします。
そうやって、「数える」行為を「集合数を把握する」行為に進展させていきます。
5個まで取り出せたら
5個まで取り出せたら、その数を10個まで延ばしていきます。
その際、取り出したおはじきを、5個で区切って並べるようにアドバイスします。
こうすると、個数が把握しやすくなります。
また、5をまとまりとして意識させることで、より柔軟な数の操作が可能になります。
- 6個 :○○○○○ ○
- 7個 :○○○○○ ○○
- 8個 :○○○○○ ○○○
- 9個 :○○○○○ ○○○○
- 10個:○○○○○ ○○○○○
【課題3】数字で指定された個数を取り出す(10個まで)
用意するもの:
おはじき(10個以上)
手続き
おはじきの山(10個以上)を子どもの前に置きます。
紙に書いた1~10の数字をランダムに見せて、その個数を取り出してもらいます。
これを数回試行します。
チェックポイント
紙に書いてある数字の個数を数えて取り出すことができればOKです。
取り出す要領は、課題2と同じです。
これをクリアできた子どもは、数字が表す大きさを理解しています。
数字の大きさを理解することの意味
子どもが基数を理解したあと、早い段階で数字が表す大きさを理解することは、重要な意味をもっています。
数字の大きさを理解すると、カードゲームやボードゲームで遊べるようになるなど、数的活動の範囲が格段に広がり、数的発達が加速するからです。
数字の表す大きさを理解するためには、基数を理解することと、数字を覚えることの二つが達成されなければなりません。
この二つが達成されてはじめて、両者のマッチング始まります。
したがって、この段階でまだ数字を覚えていない子どもには、早急に数字を覚える機会を作ってあげてください。
数字を覚える機会をどう作るかについては、ステップ2で解説しています。
【数字ポスターの選び方のポイント】
・100までの数字が表になっているもの(100以上ならよい)
・一の位の数が列ごとに揃っているもの(11~100が揃っていればよい)
以下は、家庭の学びのスタイル、お子さんの発達状況に合わせて選択
・数字に読み仮名がついているかどうか
・お風呂に貼れるかどうか
・1~10に具体物の例があるかどうか
- Geary D. C., van Marle K., Chu, F. W., Rouder J., Hoard M. K., & Nugent L. (2018). Early conceptual understanding of cardinality predicts superior school-entry number-system knowledge. Psychological Science, 29(2), 191–205.
- 栗山 和弘 (1993). 幼児の数表象の構造, 宮崎女子短期大学紀要, 第20号, 29−37.
- 丸山 良平, 無藤 隆 (1997). 幼児のインフォーマル算数について. 発達心理学研究, 第8巻, 第2号, 98−110.
- Chi, M. T., & Klahr, D. (1975). Span and rate of apprehension in children and adults. Journal of Experimental Child Psychology, 19(3), 434–439.
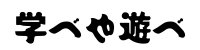
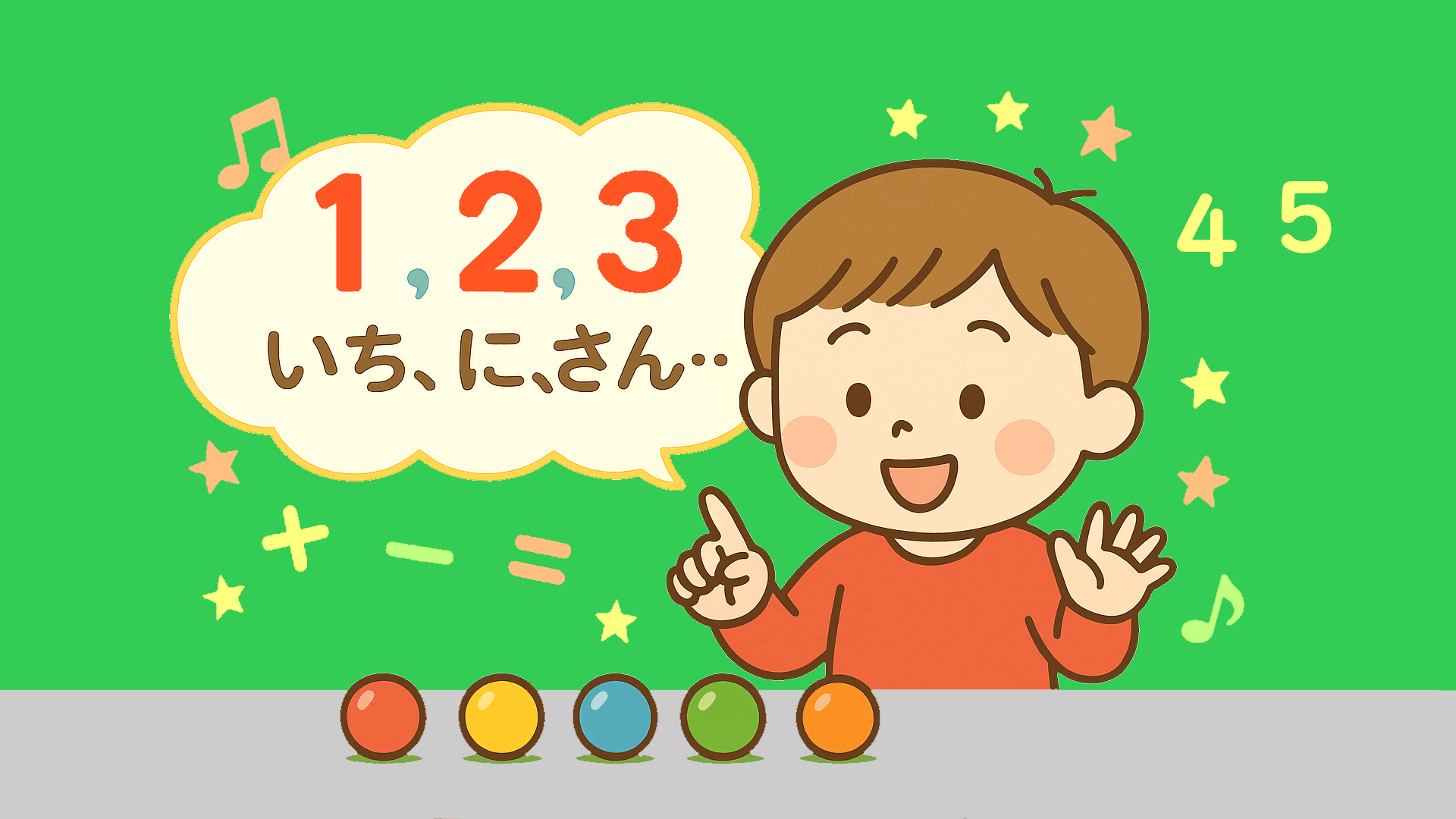



子どもの学びに関する多くの学術的知見を持っています。
また、6歳児から中高校生まで勉強を教えた経験があり、学力に与える学習の効果は、年齢が低いほど大きいことを痛感しています。
これらを生かして、効果的で再現性の高い子どもの学びのあり方や方法を提案していきます。よろしくお願いします。