数の力を身につける18ステップ!
家庭でできるチェック&トレーニング【ステップ11】
習得目標年齢:5歳
▶ 前のステップへ:【ステップ10】いろいろな範囲の数を唱える
【ステップ4】合わせていくつ?❶からの発展課題です。
扱う数の範囲を10まで拡大するとともに、計算方略の進展をはかっていきます。
| 【ステップ4】 | 【ステップ11】 | |
|---|---|---|
| 扱う個数 | 5個まで | 10個まで |
| 用いる方略 | カウント・オール | 数え足す方略 5のまとまりを意識した方略 |
幼児が使う計算方略と後の算数の成績には強い相関があります。
このステップは少し時間がかかるかもしれませんが、じっくり取り組んでほしいと思います。
【課題】具体物を見ないで数を足し合わせる
用意するもの:
おはじき(10個以上)、容器(カップやお椀)
手続き
- 子どもの前におはじきの山を置く。
- 子どもに、おはじき4個をカップに入れるように言う。
→ (子ども)山からおはじきを4個取ってカップに入れる。 - さらにおはじきを3個カップに入れるように言う。
→ (子ども)山からおはじきを3個取ってカップに入れる。 - 「カップの中のおはじきは何個?」と尋ねる。
→ 子どもがカップに入れた個数を覚えていない場合は、「最初に4個、後から3個入れたよ」などと言って、入れた個数を再度伝える。
このような手続きで、二つの集合を合わせたときの個数(10個まで)を問います。
なお、[出題例]①~⑩の個数の求め方は、次の「チェックポイント」の後半で個別に解説しています。
チェックポイント
この課題では、入れた個数の和が求められることはもちろん、「カウント・オール方略」(ステップ4)からの計算方略の進展を見ていきます。
幼児が用いる方略はさまざまですが、この段階では、次の「ⓐ 数え足す方略」か「ⓑ 5のまとまりを意識した方略」で個数が求められるとよいです。
では、それぞれのやり方を見ていきましょう。
ⓐⓑとも、最初にセットする個数が「4個以下の場合」の例と「5個以上の場合」の例を示しています。
ⓐ 数え足す方略
 |
① 片ほうの手の指を4本立てる(4をセットする)。
|
 |
② 3を加える操作として、同じ手の残りの指を立てて「ご」と言ってから、もう片ほうの手に移り「ろく、なな」と数え足す。
|
 |
|
 |
 |
① 左右の手で6をつくる(5本と1本)。
|
 |
② その続きを、指を立てながら「なな、はち」と足していく。
|
 |
また、数え足しのバリエーションとして、次のような方略があります。
足した数を指でカウントする方略
たとえば、4に3を加える場合、(指を立てずに)4を覚えておいて、そこから「ご、ろく、なな」と唱えながら、指を折って足した数をカウントしていきます。
この場合、指は足した数を確認するために使います。
このやり方だと、「いくつ足したか」分からなくなってしまうことがないので、より大きな数を足すことができます。
数の順番から和を求める方略
加える数が少ないとき(1か2のとき)は、数の順番から瞬時に答えを導すことができます。
たとえば、5に1を加える場合、「5より1つ大きい数は6」という具合に和を求めます。
ⓑ 5のまとまりを意識した方略
 |
① 片ほうの手の指を4本立てる(4をセットする)。
|
 |
② 「まず、1つ(足して)」などと言って、同じ手の残りの指を1本立てて5本にする。
|
 |
③ 「あと2つだから」などと言って、もう片ほうの手の指を2本立てる。➜ 5本と2本の指を見て「(5と2で)なな」
|
* 指の使い方からは、ⓐの数え足しと区別できない場合があります。
 |
① 片ほうの手の指を4本立てる(4をセットする)。
|
 |
② 3を加える操作として、もう片ほうの手の指を3本立てる。
|
 |
③ 3本の指のうちの1本を4本のほうに移動させて、5のまとまりをつくる。➜ 5本と2本の指を見て「(5と2で)なな」
|
 |
① 左右の手で6をつくる(5本と1本)。
|
 |
② 2を加える操作として、1本のほうの手の指をもう2本立てて3本にする。➜ 5本と3本の指を見て、「(5と3で)はち」
|
* 指の使い方からは、ⓐの数え足しと区別できない場合があります。
①(5,2)
- 5をセットして、2を数え足す。(方略ⓐ)
- 指を5本と2本立てて、「5と2で7」。(方略ⓑ)
②(5,5)
- 指を5本と5本立てて、「5と5で10」。(方略ⓑ)
「5のまとまりが二つ」という見方をします。
③(4,3)
方略ⓐⓑの解説を参照。
④(2,4)
やり方は③と同じです。
- 2をセットして、4を数え足す。(方略ⓐ)
- 2をセットして、4を3,1の順に足す。(方略ⓑその1)
- 指を2本と4本立てて、2本の指の1本を4本ほうに移動する(1本と5本の形)。※
→ 「1と5で6」(方略ⓑその2)
※ 4本の指の3本を2本ほうに移動する(5本と1本の形)よりも簡単(合理的)です。
⑤(6,2)
方略ⓐⓑの解説を参照。
⑥(7,3)
やり方は⑤と同じです。
- 7をセットして、これに3を足す。(方略ⓐⓑ)
⑦(2,5)
- 指を2本と5本立てて、 「2と5で7」。(方略ⓑ)
5を崩さずに、そのまま生かすのがポイントです。
⑧(4,5)
考え方は⑦と同じです。
- 指を4本と5本立てて、 「4と5で9」。(方略ⓑ)
⑨(1,8)
1に8を数え足すのは、大変です。いくつ足したかもわからなくなってしまいます。
このように足す数が大きいときは、「足した数を指でカウントする方略(方略ⓐのバリエーション)」か「方略ⓑ」を用いると、混乱せずに計算できると思います。
なお、この二つでは、数構成の理解につながる「方略ⓑ」を推奨します。
- 1をセットして、8を4、4の順に足す。(方略ⓑ)
さらに一歩進んで、足される数と足す数を逆にすると、より簡単に計算できることに気付かせるようにします。
- 8をセットして、1を足す。(方略ⓑ)
この方法については、「練習のポイントのステップ③」で解説しています。
⑩(2,6)
考え方は⑨と同じです。
- 2をセットして、6を3と3の順に足す。(方略ⓑ)
- 6をセットして、2を足す。(方略ⓑ)
なお、④(2,4)についても、「2<4」なので、4に2を加えるほうが容易です。
4がそれほど大きい数ではないので、大差はないと思いますが。
練習のポイント
ステップ① カウント・オールから数え足しへ
子どもがまだカウント・オールに頼っているようなら、教示者が指の使い方をアドバイスしたり、実演したりして、まずはⓐの数え足す方略に導いていきます。
出題例①~⑩の一巡目は、全て数え引きでやってみるのも一つの手です。
ステップ② 5のまとまり意識を向けさせる
数え足しをマスターしたあとは、5のまとまりに意識を向けるように促していきます。
こちらのほうが方略としては発展性があります。
5のまとまりを意識している子どもは、5をまとめると集合数を把握、操作しやすいことを理解しています。
また、就学後に学ぶ繰り上がりのあるたし算にも、適応が容易です。
「数え足し」から「5のまとまりを意識した方略」に向う流れとしては、
たとえば4に3を数え足すとき、「よん、ご、(一拍置いて)ろく、なな」という具合に、5を強調して(手でも強調)、子どもの意識が5に向かうようにしていきます。
そして次の段階で、5のまとまりを意識した方略を取り入れていきます。
ステップ③ 「足す数」に「足される数」を足してもよいことを理解させる
たとえば、2個に6個を加える場合、2をセットして、それに6を足すのは、計算の流れとして自然です。
しかし、数え足しで「さん,よん,ご,ろく,なな,はち」と、6回足すのは大変です。
足す数が多くなると、いくつ足したかも分からなくなってしまいます。
これを、「足される数」と「足す数」を逆にする、つまり6に2を足すようにすると、「なな,はち」と、2回数え足すだけで済みます。
このほうが早くて確実です。
「5のまとまりを意識した方略」を使う場合も、2に6を2回に分けて足すよりも、6に2を1回足すほうがずっと簡単です。
もし、子どもがあとに入れた個数が十分に多いとき([出題例]の⑨⑩のようなケース)でも、先に入れた個数をセットして計算していたら、大きいほうの数をセットしたほうが、計算が容易であることに気づかせるようにします。
- 教示者:(おはじきを2個をカップの中に入れて、子どもに確認させる)
- 教示者:「今、カップの中に何個ある?」
- 子ども:(指を1本立てる)
- 教示者:「最初、何個あった?」
- 子ども:「2個」
- 教示者:(カップに6個のおはじきを加えて)「今6個入れたよ。全部で何個なったかな?」
- 子ども:(2に6を足しはじめる)
- 教示者:(少し待ったあと)「2に6を足すのは大変だね。2を6に足しても、6に2を足しても、全部の数は同じだよ」(と言って、おはじきを使って実演する)
←
→ - 子ども:(6をセットして「なな、はち」と数えて)「8個」
このようにして、足し方を逆にしても、合わせた数に変わりがないことへの理解を促していきます。
なお、状況に応じて方略を選択的に使用することは、数学が強くなるのに必須とされる「ナンバーセンス」を育むのに非常に重要とされています。
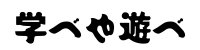
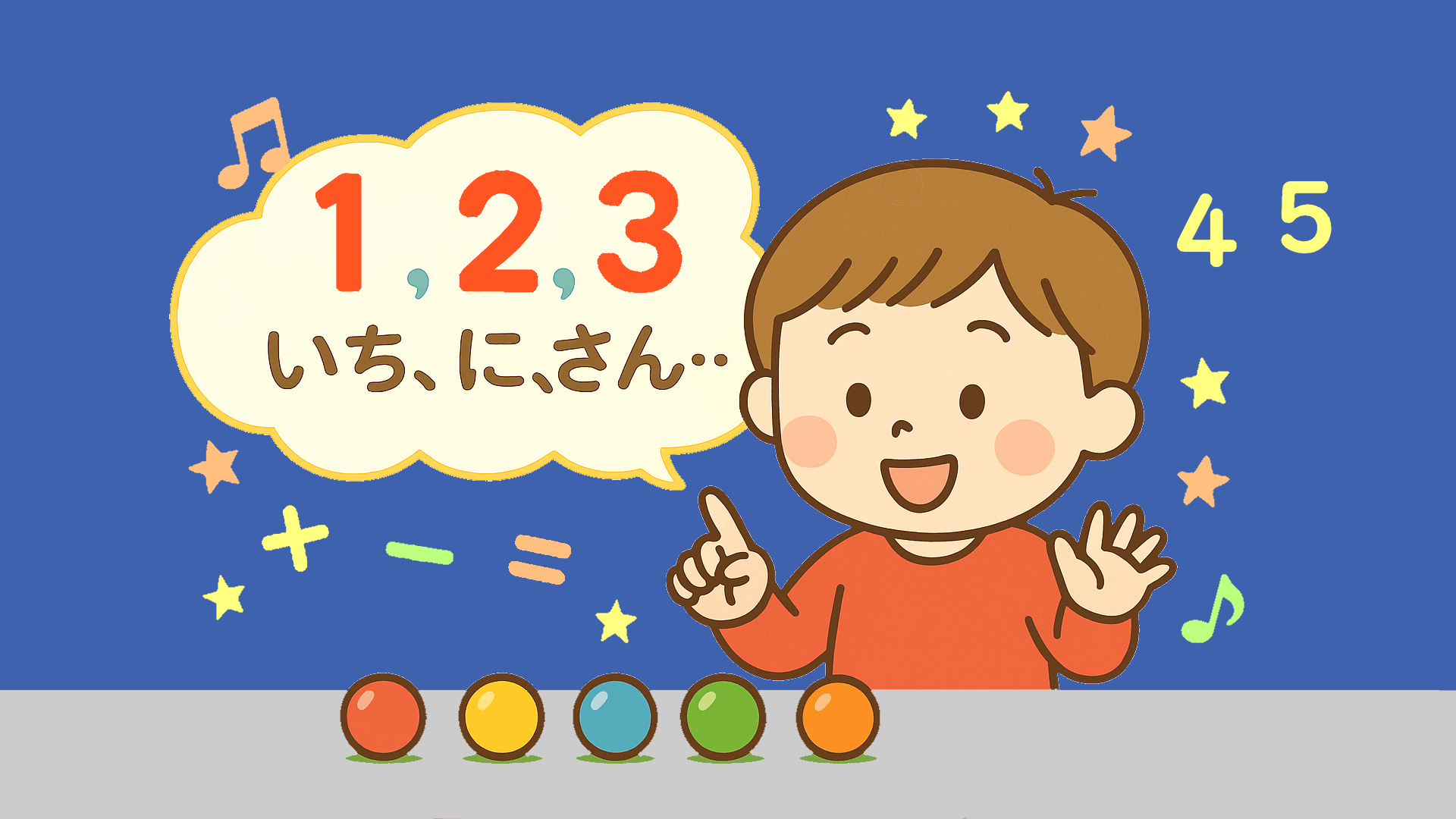


子どもの学びに関する多くの学術的知見を持っています。
また、6歳児から中高校生まで勉強を教えた経験があり、学力に与える学習の効果は、年齢が低いほど大きいことを痛感しています。
これらを生かして、効果的で再現性の高い子どもの学びのあり方や方法を提案していきます。よろしくお願いします。