数の力を身につける18ステップ!
家庭でできるチェック&トレーニング【ステップ14】
習得目標年齢:5歳半~6歳半
▶ 前のステップへ:【ステップ13】こっちの手には何個ある?❷
【ステップ12】残りはいくつ?と対になる課題です。
【ステップ12】では、ものの集合からいくつかを取り除き、「取り除いた個数」から「残りの個数」を求めましたが、【ステップ14】では、「残りの個数」から「取り除いた個数」を求めます。
これによって、ひき算の考え方(概念)を拡張します。
【課題】取り除いた個数を求める
用意するもの:
おはじき(10個)、容器(カップやお椀)
手続き
- おはじきを7個カップに入れる。
→「今、カップの中に7個あるよ」と言って、子どもに個数を確認させる。 - カップからおはじきを5個取り出す。
→ このとき、取り出したおはじきを、子供に見せないようにする。 - 子どもに、カップにおはじきが2個残っていることを確認させてから、「今、何個取った?」と尋ねる。→ 子どもがセットした個数を覚えていない場合は、「最初、カップに7個入れたよ」などと言って、セットした個数を再度伝える。
このような手続きで、ものの集合(6~10個)からいくつかを取り除き、残っている個数を見せて、取り除いた個数を問います。
数構成の理解と、方略の使い分けを促すために、①と②、③と④、⑤と⑥、…をセットで出すようにしています。
チェックポイント
【ステップ12】残りはいくつ? と、表裏の関係にあります。
・【ステップ12】もとの個数 - 取り除いた個数 = 残りの個数
・【ステップ14】もとの個数 - 残りの個数 = 取り除いた個数
用いる方略は同じですが、ステップ12が実際の操作と計算が一致するのに対し、ステップ14は一致しないので、こちらのほうが難易度が高いです。
取り除いた個数の求め方としては、
ⓐ 一般に、カップの中に残っている個数が少ないとき(出題例の①③⑤⑦⑨)は、セットした個数から残っている個数を引くほうが容易です。
たとえば、①は、「もとの個数6個 」から「残っている個数1個」を引いて、(取り除いた個数は)「5個」という具合に求めます。
ⓑ セットした個数の大部分が残っているとき(出題例の②④⑥⑧⑩)は、補数で考えると容易な場合が多いです。
たとえば、➁は、「残っている個数5個」に「1個」を足すと「もとの個数6個 」になるから、(取り除いた個数は)「1個」という具合に求めます。
ⓐⓑのどちらでやるか迷った場合は、ⓐの方略でやっておけばよいです。
ⓒ 数の構成が頭に入っていれば、瞬時に個数を求めることができます。
たとえば、①➁は、「1と5で6」または「6は1と5」という数構成の知識を利用します。
ⓐやⓑの方略に習熟すれば、自然にこの方略に移行します。
練習のポイント
「取り除いた個数」と「残っている個数」の関係が理解できない子どもには、次の要領で、両者の関係性の理解を促していきます。
- 教示者:(おはじき6個を子どもと一緒に数えて、カップの中に入れる)
- 教示者:(カップから2個取り出し、手に握る)
- 教示者:「今、カップの中は何個?」
- 子ども:(カップの中を見て)「4個」
- 教示者:(握っている手を振って)「こっちが取り出したおはじきだよ。何個あるかな?」
- 子ども:「・・・」
- 教示者:「最初6個あったでしょ。こっち(カップ)に4個あるから・・・ 」
- 子ども:「2個?」
- 教示者:(手を開いて)「そう、『この4個に2個を足すともとの6個になるから2個』だね。『最初の6個からこの4個を取って2個』と考えてもいいよ」
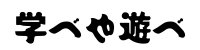
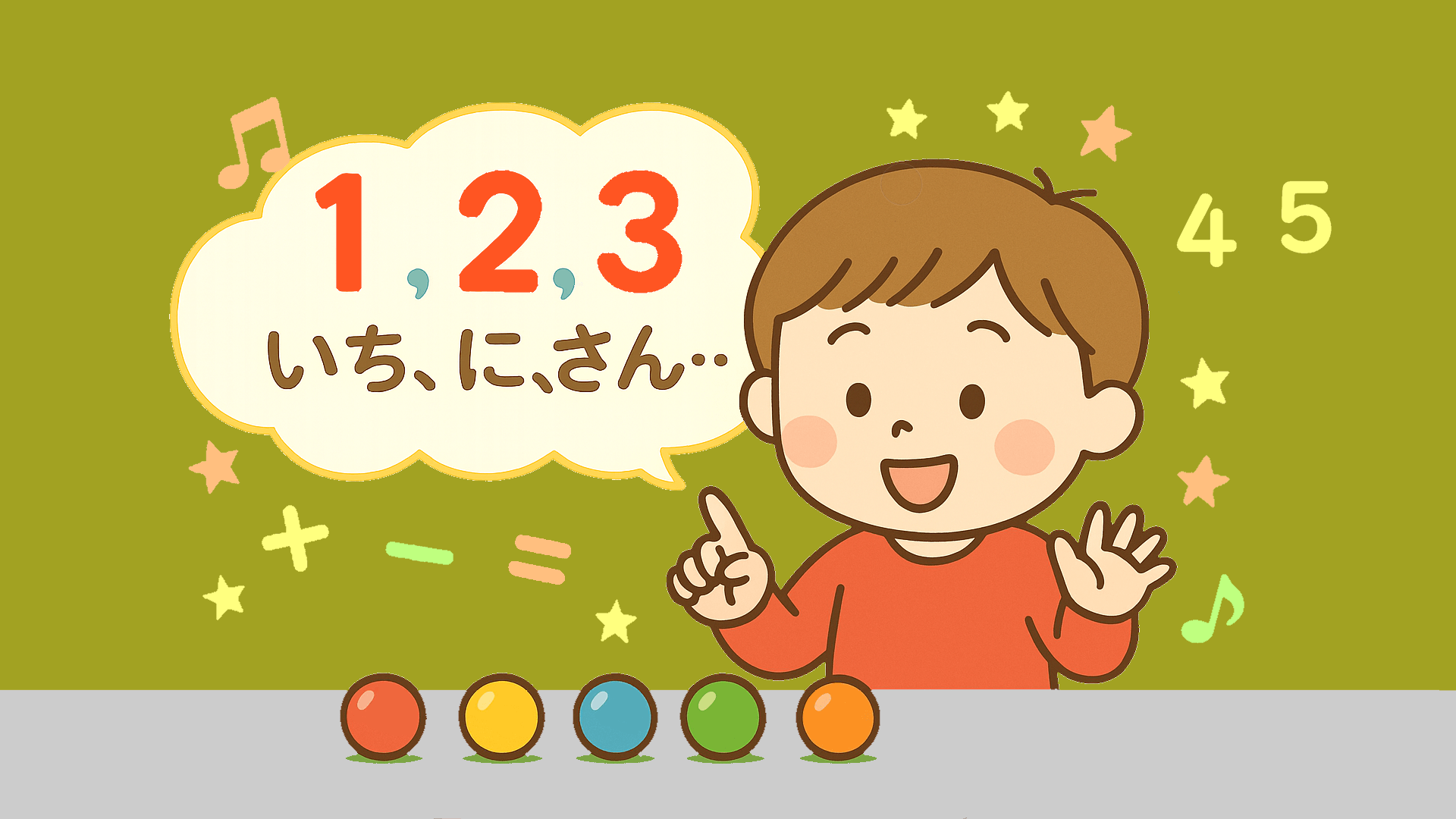


子どもの学びに関する多くの学術的知見を持っています。
また、6歳児から中高校生まで勉強を教えた経験があり、学力に与える学習の効果は、年齢が低いほど大きいことを痛感しています。
これらを生かして、効果的で再現性の高い子どもの学びのあり方や方法を提案していきます。よろしくお願いします。