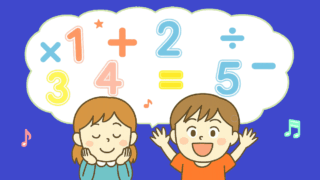 小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び 【家庭で教える算数】『3つの数の計算』でナンバーセンスを育てよう!(小学校2・3年)
小学校の2年生で学習する「3つの数の計算(たし算・ひき算)」は、工夫すると簡単になるケースが多く、ナンバーセンスを磨くのに適している。この「3つの数の計算」の効果的な学習方法を解説。
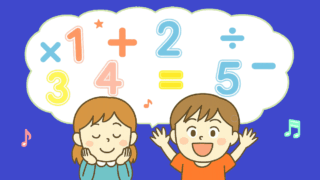 小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び  小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び 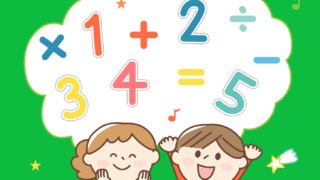 小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び 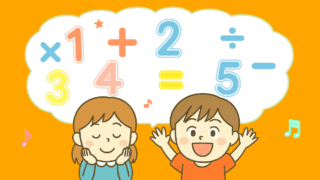 小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び 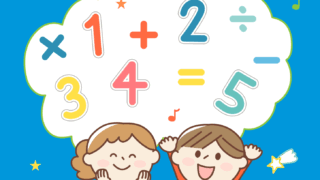 小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び  小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び 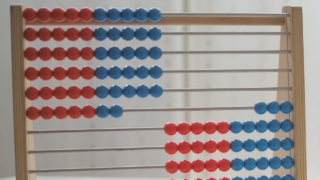 小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び  小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び  小学期(低学年)の学び
小学期(低学年)の学び