「自分の子どもは、数をきちんと理解しているのか?」、「理解が遅れてはいないだろうか?」と不安に思ったことはありませんか?
この記事は、そんな親御さんたちををサポートするためにまとめたものです。
対象となる子どもは、3歳から6歳ぐらいです。
はじめに:なぜ幼児期に「数的能力」を育てることが重要か?
幼児期から小学校初期に身につけた「数の力」は、その後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。
実際に、学童期、特に小学校初期の算数のパフォーマンスが、学力全体、そして将来の成果までに影響を及ぼすことが、多くの研究から分かっています。※
それだけに、「数の学び」は知育の中でも特に重視すべき領域といえるのです。
子どもの数の発達には順序性があります。
ある段階で身につけるべき知識を欠いていたり、概念の理解が不十分たったりすると、新しいことを学ぶときにつまずきやすくなります。
そしてそれを放置すると、算数の学習が困難になっていきます。
そのため、数の知識やスキルは「一つひとつ、順を追って、確実に」積み上げていく必要があります。
幼児の数の学びは、「インフォーマルな算数(生活や遊びの中で身につける算数)」が中心になりますが、親がその進展をときどき確認し、必要に応じて補完、修正してあげると、お子さんの数の理解を着実に進めることができます。
では、
子どもの数の理解が順調に進んでいるかどうかは、どうやって確認すればよいのでしょうか?
また、理解が不十分な場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?
このような悩みに応えるために、発達の段階を踏んだ“18のステップ”を用意しています。
チェックとトレーニングを通して、お子さんの数の知識とスキルの習得をサポートします。
※ たとえば、Duncan et al, 2007; Claessens, Duncan & Engel, 2009; Jordan et al, 2009; Siegler et al., 2012; Watts et al., 2014; Bailey, Siegler & Geary, 2014; Nguyen et al., 2016(文献の詳細は記事下)
「ステップ1~18」へのリンクは、記事の最後に設置しています。このプログラムの特徴
このプログラムは、発達の順序にそって18のステップで構成されています。
各ステップには、
- 発達の順序を考慮した段階的なチェック課題
- 家庭でできるトレーニングの方法
- 指導のポイントや注意点
が含まれています。
また、「課題」には、のちの算数の学力の予測因子として特定されている「数の知識とスキル」が含まれています。
18のステップの内容と進め方
それぞれのステップで扱う内容と、習得の目標となる年齢を、下の表にまとめています。
「ステップ1」は、3歳ごろからのスタートとなりますが、発達には個人差があります。
あまり年齢にとらわれることなく、お子さんの発達に応じて、一つ一つ、数の知識とスキルを積み上げていってください。
もちろん、途中から始めることもできます。
ステップ18まで達成すると、数の「構造」「関係」「まとまり」「操作」に対する理解が深まり、就学後の学びに自信をもって臨めるようになります。
また、その後の算数の学習でも、ポジティブな軌道に乗る可能性が高くなります。
| ステップ | 内容 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数を唱える➊(1から10まで) | ● | ● | ||||||
| 2 | ものを数える(10個まで) | ● | ● | ||||||
| 3 | ものを取り出す➊(10個まで) | ● | ● | ||||||
| 4 | 合わせた個数を求める➊(5個まで) | ● | ● | 5 | 残りの個数を求める➊(もとの個数:5個まで) | ● | ● | 6 | 〇番目を特定する(10番目まで) | ● | ● | 7 | 隠れている個数を求める➊(全体の個数:5個まで) | ● | ● | 8 | ものを取り出す➋(20個まで) | ● | ● | 9 | 個数差を求める➊(比べる個数:5個まで) | ● | ● | 10 | 数を唱える➋(1から10、10から1の任意の範囲) | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 合わせた個数を求める➋(10個まで) | ● | ● | ||||||
| 12 | 残りの個数を求める➋(もとの個数:10個まで) | ● | ● | ||||||
| 13 | 隠れている個数を求める➋(全体の個数:10個まで) | ● | ● | ||||||
| 14 | 取り除いた個数を求める(もとの個数:10個まで) | ● | ● | ||||||
| 15 | 個数差を求める➋(比べる個数:10個まで) | ● | ● | ||||||
| 16 | 合わせていくつ増えたかを求める(5個まで) | ● | ● | ||||||
| 17 | 合わせていくつ減ったかを求める(5個まで) | ● | ● | ||||||
| 18 | 差し引きでいくつ増えたか・減ったかを求める (5個まで) |
● | ● | ||||||
※ 発達の順序性および習得目標年齢については、三浦, 西谷, 1976; 山内, 松本, 安齊, 1997; 山内, 松本, 安齊, 1998; 大塚, 2000; 丸山, 2002; 古池, 2014 を整理・統合し、筆者の経験的判断を加えて作成しています。(文献の詳細は記事下)
「ステップ1~18」へのリンクは、記事の最後に設置しています。よくある質問
Q.数の理解が 習得目標年齢よりも遅れていたらどうなりますか?
習得目標年齢はあくまでも目安です。
幼児の数的発達には個人差があります。
また、年少、年中、年長などのくくりで見ると、生まれた月による差も大きいです。
この差自体は、たいした問題にはなりません。
それよりも、最初にお話ししたように、身につけるべき知識や概念を欠いたまま進んでいくことのほうが、ずっとリスクが大きいです。
あせらずに、数の知識とスキルを一つ一つ積み上げ、しっかりとした土台を作ることを目指してください。
なお、子どもの数的理解の遅れは、
① 家庭での数的活動を充実させる。
② 親が必要に応じて教示を施す。
ことで取り戻すことができます。
しかし、それを放置してしまうと、取り戻すのがどんどん大変になっていきます。
そのためにこの「チェック&トレーニング」をご活用ください。
ステップごとに、指導や教示の方法などをまとめてあります。
なお、就学までにステップ12あたりまで達していれば、正式な算数の学習に問題なく入っていけます。
18まで達していれば、就学後の算数の学習でかなりのアドバンテージが得られるでしょう。
Q.この「チェック&トレーニング」だけで、算数の基礎が身につくのでしょうか?
幼児は、家庭でのインフォーマルな活動(遊びや生活活動)を通じて、算数の基礎となる数の知識とスキルを身につけていきます。
たとえば、日常の会話ややりとり、トランプやボードゲームなどを通じて、ものを数えたり、数量を比べたり、数を合計したりすることを学びます。
このインフォーマルな算数が、幼児の算数の能力の発達に非常に重要な役割を果たしていることは、たくさんの研究からわかっています。※
したがって、幼児の数の学びは、数に関するやりとりや、数的要素のある活動をたくさん経験させるのが望ましいです。
親としても、直接教示するよりも、そのほうが楽です。
しかし、インフォーマルな活動だけでは、ある部分の知識が不足していたり、そうでなくても、体系的な知識として整えられていなかったりするので、そこは親がしっかり補完してあげる必要があります。
そのために、この「チェック&トレーニング」を役立ててほしいと思います。
もっとも、この「チェック&トレーニング」をしっかりやると、インフォーマル算数を「補完」する以上に、算数の基礎となる「数の知識とスキル」を一段と高いレベルに引き上げることができます。
※ たとえば、LeFevre et al., 2009; Gunderson & Levine, 2011; Ramani et al., 2015; Casey et al., 2016; Susperreguy & Davis-Kean, 2016; Gibson, Gunderson & Levine, 2020(文献の詳細は記事下)
各ステップへのリンク
【ステップ7】こっちの手には何個ある?❶(全体の個数:5個まで)
【ステップ9】どちらがいくつ多い?❶(比べる個数:5個まで)
【ステップ10】いろいろな範囲の数を唱える(10以下の範囲)
【ステップ13】こっちの手には何個ある?❷(全体の個数:10個まで)
【ステップ15】どちらがいくつ多い?❷(比べる個数:10個まで)
【ステップ16】いくつ増えた?(加える個数の合計:5個まで)
【ステップ17】いくつ減った?(取り除く個数の合計:5個まで)
【ステップ18】いくつ増えた?・減った?(加える個数、取り除く個数:5個まで)
- Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., & Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43: 1428–1446.
- Claessens, A., Duncan, G., & Engel, M. (2009). Kindergarten skills and fifth-grade achievement: evidence from the ECLS-K. Economics of Education Review 28(4): 415-427.
- Jordan, N. C., Kaplan, D., Ramineni, C., & Locuniak, M. N. (2009). Early math matters: kindergarten number competence and later mathematics outcomes. Developmental Psychology. 45(3): 850–867.
- Siegler, R. S., Duncan, G. J., Davis-Kean, P. E., Duckworth, K., Claessens, A., Engel, M., Chen, M. (2012). Early Predictors of High School Mathematics Achievement. Psychological Science, 23(7): 691–697.
- Watts, T. W., Duncan, G. J., Siegler, R. S., & Davis-Kean, P. E. (2014). What’s past is prologue: Relations between early mathematics knowledge and high school achievement. Educational Researcher, 43: 352–360.
- Bailey, D. H., Siegler, R. S., & Geary, D. C. (2014). Early predictors of middle school fraction knowledge. Developmental Science, 17: 775–785.
- Nguyen, T., Watts, T. W., Duncan, G. J., Clements, D. H., Julie S. Sarama, J. S., Wolfe, C., & Spitler, M. E. (2016). Which Preschool Mathematics Competencies Are Most Predictive of Fifth Grade Achievement? Early Childhood Research Quarterly 36: 550-560.
- 大塚 玲 (2000). 幼児の加減算習得にいたる数の理解に関する発達順序性. 静岡大学教育学部研究報告 教科教育学篇, 31, 259-270.
- 古池 若葉 (2014). 幼児における数概念と数字の読みの因果関係. 京都女子大学発達教育学部紀要, 010, 87-91.
- 丸山 良平 (2002). 幼稚園に就園する3年間で幼児が習得する数唱と数詞系列の実態. 上越教育大学研究紀要, 22(1), 119-132.
- 三浦 香苗, 西谷 さやか (1976). 幼児の数量概念と診断テストの作成. 千葉大教育学部紀要, 第25巻, 第1部.
- 山内 昭道, 松本 尚子, 安齊 智子 (1997). 幼児期の数概念形成についての研究 第1報 問題の所在と数唱と計数の調査研究. 東京家政大学研究紀要, 第37集(1), 197-204.
- 山内 昭道, 松本 尚子, 安齊 智子 (1998). 幼児期の数概念形成についての研究 第2報 幼稚園と保育園の幼児の比較. 東京家政大学研究紀要, 第38集(1), 109~117.
- LeFevre, J. A., Skwarchuk, S. L., Smith-Chant, B. L., Fast, L., Kamawar, D., & Bisanz, J. (2009). Home numeracy experiences and children’s math performance in the early school years. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 41, 55.
- Gunderson, E. A., & Levine, S. C. (2011). Some types of parent number talk count more than others: Relations between parents’ input and children’s cardinal-number knowledge. Developmental Science, 14, 1021–1032.
- Ramani, G. B., Rowe, M. L., Eason, S. H., & Leech, K. A. (2015). Math talk during informal learning activities in Head Start families. Cognitive Development, 35, 15–33.
- Casey, B. M., Lombardi, C. M., Thomson, D., Nguyen, H. N., Paz, M., Theriault, C. A., & Dearing, E. (2016). Maternal support of children’s early numerical concept learning predicts preschool and first-grade math achievement. Child Development, 89, 156–173.
- Susperreguy, M. I., & Davis-Kean, P. E. (2016). Maternal math talk in the home and math skills in preschool children. Early Education and Development, 27, 841–857.
- Gibson, D.J., Gunderson, E.A., & Levine, S.C. (2020). Causal Effects of Parent Number Talk on Preschoolers’ Number Knowledge. Child development, Vol. 91, No. 6, Pages e1162-e1177.
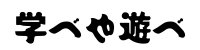
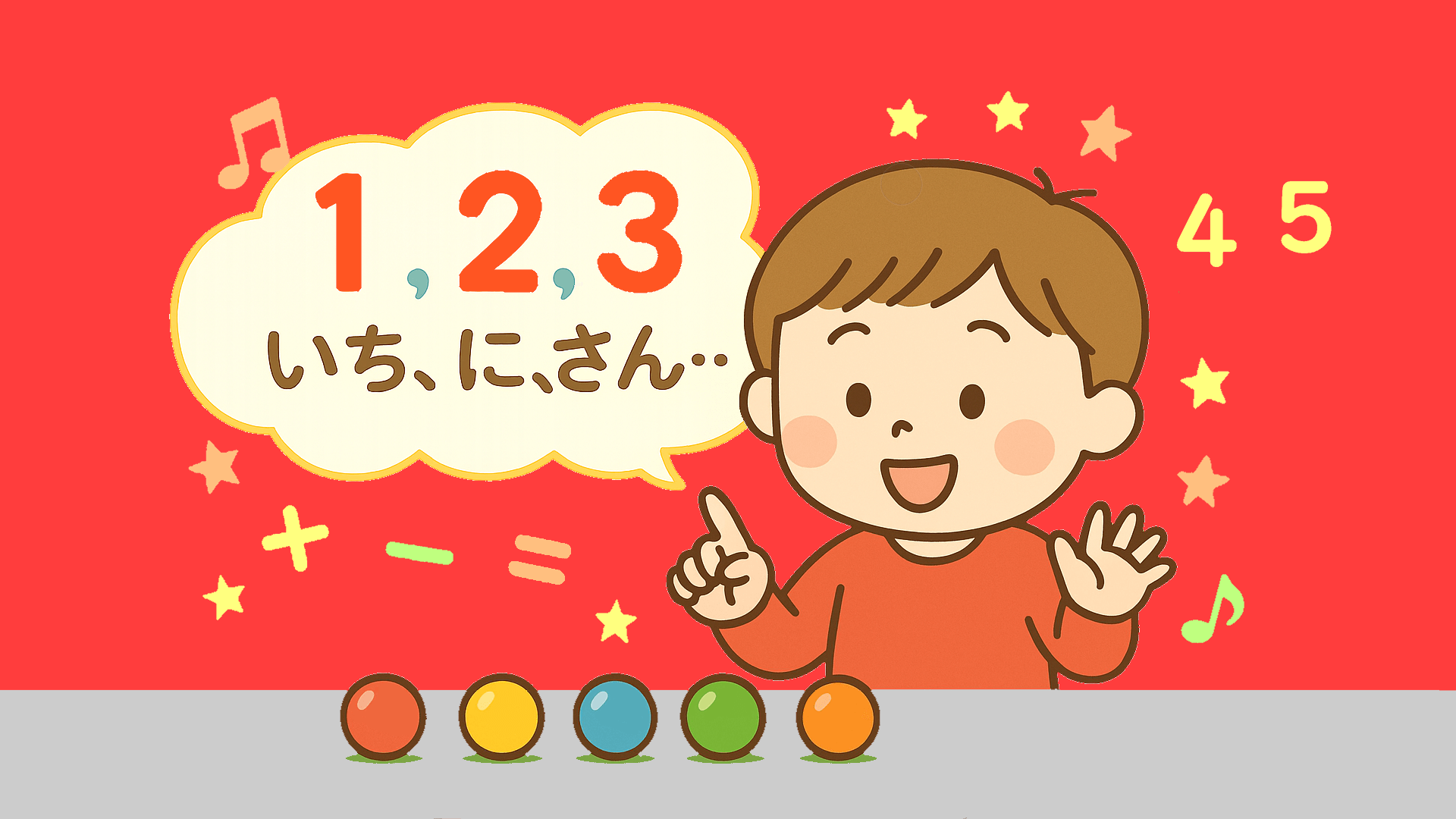


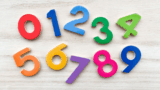
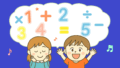

子どもの学びに関する多くの学術的知見を持っています。
また、6歳児から中高校生まで勉強を教えた経験があり、学力に与える学習の効果は、年齢が低いほど大きいことを痛感しています。
これらを生かして、効果的で再現性の高い子どもの学びのあり方や方法を提案していきます。よろしくお願いします。