数の力を身につける18ステップ!
家庭でできるチェック&トレーニング【ステップ10】
習得目標年齢:分割順唱-4歳、分割逆唱-5歳
扱う数の範囲が大きくなるにつれて、数を処理するためにより高度な計算方略が必要になります。
このステップでは、たし算、ひき算の初期の計算方略 である「数え足し」、「数え引き」の習得に備えて、任意の範囲の数を昇順にも降順にも自在に唱えられるようにしておきます。
【課題1】1から10の任意の範囲を順に唱える(分割順唱)
2から6、3から8、6から9などの任意の範囲を指定して、唱えるように言います。
この数唱ができるようになると、「数え足し」が可能になります(「数え足し」はステップ11で取り上げます)。
たとえば、4に3を足す場合、4を起点にして、「(よん、)ご、ろく、なな」と数えながら3を足せるようになります。
【課題2】1から10の任意の範囲を逆に唱える(分割逆唱)
6から2、8から3、9から6などの任意の範囲を指定して、唱えるように言います。
この数唱ができるようになると、「数え引き」が可能になります(「数え引き」はステップ12で取り上げます)。
たとえば、7から3を引く場合、7を起点にして、「(なな、)ろく、ご、よん」と数えながら3を引けるようになります。
チェックポイント
チェックポイントは、指定されたところから唱え始めて、途中を飛ばすことなく、指定されたところで停止できることです。
練習のポイント
まだスムーズに唱えられないようなら、お風呂の時間を利用するなどして、遊び感覚で繰り返し練習するようにしましょう。
このとき、指を立てたり(順唱)、折り畳んだり(逆唱)しながら唱えるようにすると効果的です。
たとえば、4から8まで唱える場合、まず左手の指を4本たてます。(右手でもかまわない)
この状態で「よん」と唱えたあと、左手の指をさらに1本立てて「ご」と唱え、次に右手の指を1本づつ立てながら「ろく、なな、はち」と唱えます。
8から4まで唱えるなら、まず左手の指を5本、右手の指を3本立てて、8をつくります。(左右は反対でもよい)
この状態で「はち」を唱えたあと、指を1本づつ折り畳みながら、「なな、ろく、ご、よん」と唱えていきます。
このとき、指は3本のほうから折り畳んでいきます。
このような練習をしておくと、数え足しや数え引きがスムーズにできるようになります。
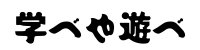
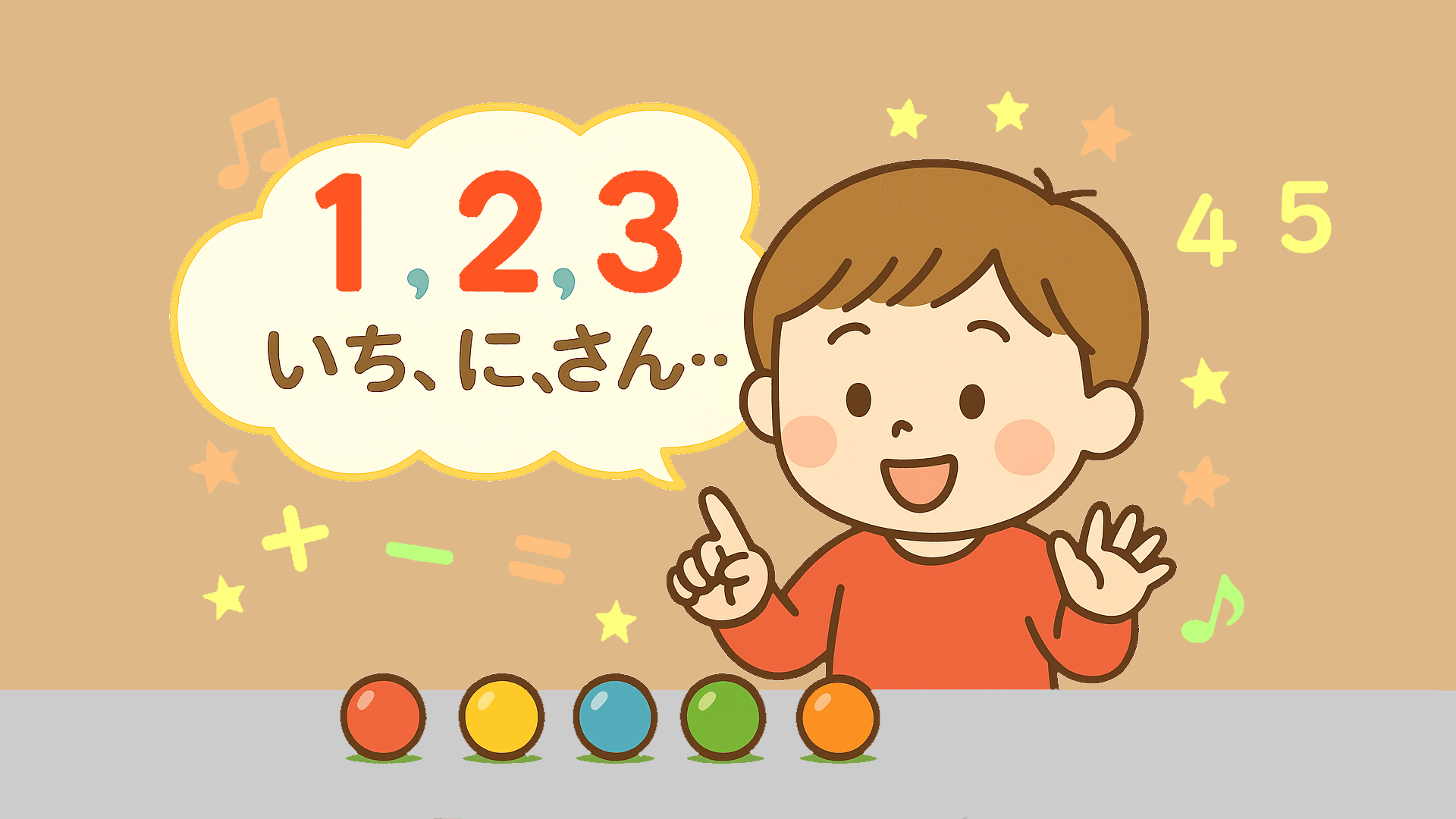


子どもの学びに関する多くの学術的知見を持っています。
また、6歳児から中高校生まで勉強を教えた経験があり、学力に与える学習の効果は、年齢が低いほど大きいことを痛感しています。
これらを生かして、効果的で再現性の高い子どもの学びのあり方や方法を提案していきます。よろしくお願いします。